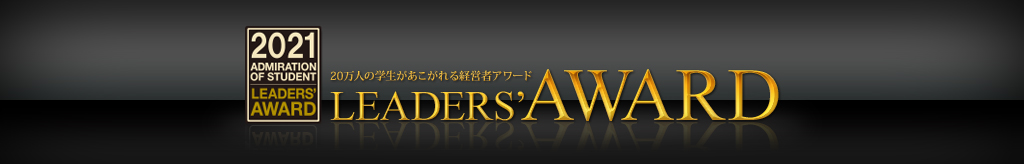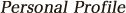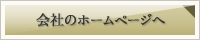私は学生時代から航空機に関心があり、大学院では航空工学を専攻。とくに航空機の設計に興味を持っていました。
その大学院1年の夏、その後の人生を大きく変える出来事が起こります。昭和60年の日航機墜落事故です。「世界一安全」といわれるジャンボ機で、なぜ大事故が起こってしまったのか解明したい。強い動機で事故原因に関する研究に没頭しました。確信したのが、空の安全は機体の設計よりも日々の整備によって守られるということ。JALには、整備士として入社しました。
以来、一整備士として、また技術部門のリーダーとして30年以上、一貫して整備に関連する仕事に従事してきました。立場は変わっても使命はただ一つ。毎日のように起こる微小な問題をつぶし、事故のリスクを限りなくゼロに近づけることです。
一日数万人の人の命を預かる仕事ですから、目標を見失うこともありませんし、辞めようと思ったこともありません。職業人として幸せなキャリアだったと思っています。

それからテクノロジーは大きく発展しました。現在、航空業界はIoT、AI、また5Gによる大きな技術発展が期待されています。ビッグデータ分析で故障リスクの高い部品を見つける「予測整備」の技術も、飛躍的に向上するはずです。私も技術者として、また航空会社のトップとして、新しいテクノロジーに大きな関心を持っています。
では、テクノロジーが発展すれば「人の目」は必要なくなるのでしょうか。答えは否です。人間が行ってきた仕事を機械が置き換えた時、人間だからこそできる仕事の重要性は、むしろ増します。確かに人間はミスをします。集中力やモチベーションが仕事の質を左右する、やっかいな存在です。しかし、知的好奇心、使命感、人間への共感といった「心」は、機械には絶対に持てないものであり、その心が、社会に変革を生み出してきました。
今の若い方々を見ると、私たちの世代より仕事に対し「世の中をより良くしたい」というモチベーションを持っている方が多く、希望を感じています。技術進歩とともに、新型コロナウイルスをはじめとした新たな課題に直面する今、航空事業には何が求められていくのか。この問いに、若い方々と一緒に挑み、価値を生み出していきたいと思っています。