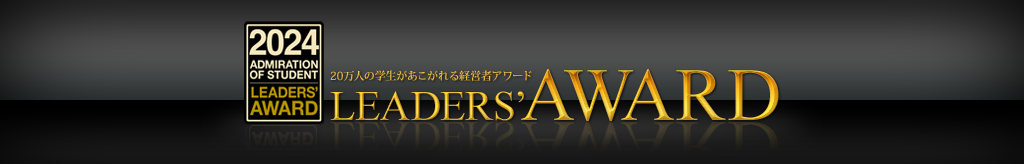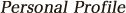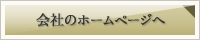私は、京都大学在学中に田杉競教授のゼミで米国経営学を学び、卒業後は地元の中堅企業に就職して人事や経理の実務を経験しました。しかし、ずっと「経営学が活かせる職業に就きたい」という思いを抱いており、26、27歳くらいの時に『マネジメント・コンサルタント その倫理と仕事のすべて』(高仲顕著)を読んだことが契機となり、30歳の時にコンサルティングファームに入社。コンサルタントの卵として新たなスタートを切ったのです。
その後、34歳で独立したのですが、当時のコンサルタント業というのは曙で、本当に休みなく働き詰めの毎日を送りました。40代になると、著書がブレークして大ベストセラーとなり、一躍有名人になって一層多忙な日々を送ることになります。
振り返ると、30代、40代、50代は本当に休みなく働き、大晦日に帰省する新幹線の中でも原稿を書いていたほど。そんな日々の中、常に意識していたのは「理論と実践の融合」でした。経営学の理論と実際の会社の経営はどういう関係になっているのかを分析し、実際に会社で実験していったのです。実験がうまくいくか、いかなければどこが悪いのかというトライ&エラーを繰り返し、理論を精緻なものにしていきました。それが私の使命だと考えていたのです。

51歳の時、ソフトハウスの社員研修を委託された会社の若手3人が、新しい会社作りについて相談に訪れました。それがきっかけで非常勤社長を引き受けるかたちで半額出資し、システム開発を中心としたホロンシステムを創業しています。
創業してすぐに急成長したのですが、4年目には米国発のダウンサイジングが日本を襲い、厳しい状況に陥りました。しかし、創業時からリスクヘッジしていたことで何とか危機を乗り越えています。そこで大切にしてきたのは、”弱気にならない“ということでした。不可能を可能にするのが”経営“であり、可能なところを見つけてトライしなければ成果は出ないのです。駄目な人ほど「こんなことはできない」と考え、できる人こそ「なんとしてもやってやる」というマインドを持っているのです。
これからの社会を創っていく若い皆さんには、自分の人生の目標を明確にし、熱狂できる仕事に就いてもらいたいと思っています。転職をする方も多くいらっしゃると思いますが、自分が目指す道へのステップアップになるところならいいのですが、「今の仕事が駄目だから」という理由で全く違った職種に就くのは自分のステージを下げることになってしまうでしょう。
そうならないためにも、「自分はこれでいこう」という進む道を早く決め、熱狂できる仕事に就くことが重要です。ぜひ自身の能力を大いに発揮してください。